
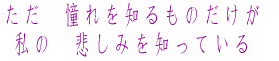
 |
僕の本棚には 学生時代に作った ガリ版刷りの 同人誌 20冊ほどと 当時のビラ数枚が 棄てられずに 残してあります。 あの時代に 活字になれなかった 散文たちを ここで やっと 活字にして あげることができました。 さとちゃん |
十七歳 佐藤 さと
思い出を大切にする人へ・・・・・
また、ひとりになっちゃった。
さよなら、
僕を好きだと
言ってくれた
景子さん。

ーあなたには ひとを愛する
資格がないのだわ。
だって、
あなたの心は
あまりにも弱すぎる。
ひとを愛するということは
とても大変なこと。
ただ闇雲に情に溺れて
一途にそのひとを信じることだけが
愛することではありません。
あなたは、知らない。
ひとを愛することの辛さを。
あなたはいつも
淡い恋の物語の主人公になったような
気持ちでいる。
私にはそれが
たまらなくらなく嫌なのです。ー
景子さんのセピア色した瞳からは
砥ぎすまされた刃物のように
嫌悪の視線が
僕の身体に突き刺さってきた。
その日の景子さんは
いつもと様子が違っていた。
いつもなら真赤なコートを着て
この珈琲店にやって来るのに
その日は真黒なコートだった。
ほとんど化粧したことのない彼女が
口紅や頬紅、つけ睫毛まで
つけてきたのだ。
僕が作った童話の話をしていても
話を聞いている様子がなかった。
会っていても、ほとんど喋ってくれなかった。
ただ
いつものように
気の強そうなあの大きな眼は
僕をしっかり凝視していた。
というより
睨んでいた。
僕も段々と
話すことが無くなって来た。
珈琲店のテーブルに向かい合っていても
二人には会話らしいものが
無かった。
彼女の視線の意味を
僕は自分なりに想像していた。
別れの予感はあった。
最近、僕と会って話しをしていても
彼女は楽しそうで
なかったからだ。

景子さんは
僕と同い年の十七歳。
友達付き合いをしてから
約一年経っていた。
僕にとっては
初めてのガールフレンドだった。
高校に入学して 初めての冬休みが
終わりそうな頃であった。
「好きです。もうじき高校が始まるから
その前に、会いたいです。」
という手紙が
彼女から届いた。
景子さんは中学三年生の時の同級生だった。
高校は違っていた。
僕は市内の男子校。
景子さんは
隣県の女子校だった。
体操部の特待生として
その女子校に入学したことは
僕も知っていた。
けれど、学校寮から
通学していた事は、知らなかった。
冬休みのほんの四、五日位の間だけ
体操部の練習が休みのため
自宅に帰ることができたらしい。
手紙の消印は
隣県のものであった。
手紙を読んでいて
僕は当惑した。
僕は恋することはあっても
恋されることなど今まで
一度も経験がなかったからだ。
それに、あの景子さんが
中学校の時
僕に好意をもっていたなんて
信じられなかった。
僕は中学三年の時の
彼女のことを
思い起こしていた。
教室で隣の席になったことがあった。
その時、僕の何気ない言葉が
彼女を
ひどく 傷つけたらしく
急に泣き出されたことがあった。
体育祭で僕が走る時
クラスの旗を振りながら
僕の名を叫んで応援してくれたこと。
下校の時、学校の下駄箱の前で
「さようーならー。」
と後ろから大きな声をかけて
くれたことがあった。
僕が振り向くと
景子さんだった。
彼女は
体操部の
ユニフォームを着ていた。
何故、わざわざ僕に
あいさつをするのだろう?
とその時、不思議に思っていた。
など
二、三、思いだしてみた。
僕にとっては
ただのクラスメイトだった。
彼女を特別に意識したことなど
一度もなかった。

初めてのデートは
名古屋の映画館だった。
その時僕は
校則どおりに学生服を着て行った。
景子さんは、その姿を見て
狼狽していた。
その帰りに公園で
戸惑いがちに赤面しながら僕は
中学校の頃のことを話していた。
彼女は、僕が学級日誌に
書いた詩を覚えていてくれた。
嬉しかった。
なきぼくろ なきぼくろ
今にも泣き出してしまいそうな 君の顔
うつむいて 涙こらえて独りきり
草笛鳴らした 子犬を抱いた
君のいじらしさ。
茶色いソバカスまだのこる あどけなさ。
どうか もう一度 笑ってくださいな。
でないと、ボッケの
キャラメル 融けちゃうよ。
中学校を卒業して以来
一年ぶりに会った景子さんは
ずいぶん大人っぽくなっていた。
話し方も落ち着いていた。
二人きりで話してみると
彼女の中学の時の
イメージとは
かなり違っていた。
僕には彼女の好意を
全く気付かなかったという負い目が在った。
僕の言葉で
泣かせてしまったという
罪の意識もあった。
「以前から気になっていたけれど
さと君はどうして
私と話しているとすぐに
下を向いてしまうの?」
「僕は眼が細くて小さいから
眼が大きい人に見詰められると
萎縮してしまうのです。」
「なあーんだ。」
と
言ってから
彼女はクククッと笑った。
「私、嫌われているのかな、
と、おもっていた。・・・」
「さと君はちっとも変わっていないね。
安心したわ。」
目立つほど美人でもなかったし、
色白でもなかった。
しかし、何より健康的で
明るい表情が
彼女の魅力なのだろう。
女の子には
唇にキスをしたい子と
頬にキスしてみたい子がいるけれども
彼女は、その頃、まだ
頬にキスしてみたいようなタイプだった。

相変わらず僕等二人の間では
会話もなく、沈黙の時間が流れていた。
ー男にはね、やさしさだけでは、
思いやりだけでは、だめなのよ。
たくましさに 支えられた
やさしさでなければ
価値はないのです。
男のやさしさだけなんて
真昼の行灯、工事現場で鳴っている
オルゴールみたいなものです。−
彼女の眼は僕を叱責している
ように感じた。
ーわかっているさ、そんなこと。−
僕も彼女を突き飛ばすような気持ちで、
眼を上げた。
しかし、彼女に視線に応えたものの
僕の心の中には
自分の人形に五寸釘を打ち抜いて
崖から一息に蹴落としてしまったような
後味の悪さが充満していた。
ーあなたは、自惚れ屋さん。
心の片隅に
自分の良さをわかってくれようとする
女の人がいる。と
固く信じているのですね・・・・。ー
彼女の眼は半ば呆れたような
嘲りの視線を送っていた。
ーだけど、だけど、そんな自惚れがなかったら、
ひとは生きていくことができません。−
僕は必死でした。
ーそこが、あなたの弱いところ。
あなたは、かつて、
片思い、片思い、と言って
哀しそうな顔をしていましたが、
一生片思いで生きることができますか?
あなたは、甘えたひと。
夜、眠る時、
あなたはいつも
指を折りながら計算しているのです。
僕が死んだら一体何人の人が
僕のことを悲しんでくれるのだろうか・・・ってね。
そのあなたの指の一本に
私を入れているのでしょう。
私が祭壇の前で
泣いている姿を想像しているのでしょう。
恐いひと。あなたは・・・・。
僕は眼をそらし、うつむいて
苦笑いをしていた。
そして
覚えたての煙草に火をつけた。
見つかれば、停学処分だ。
煙が眼に入り
涙がでそうになったけれども
僕は、こらえていた。

「僕のこと、嫌いになったのかい?」
これまでの沈黙を破り
ついに、僕は言葉をだした。
景子さんは
飲みかけのレモンティの入った
カップをさわりながら
ポツポツと
語り始めた。
「いいえ、嫌いになった、のでは
ありません。
さと君は、私といると、
傷、ついてばかりいる。
さと君は、
自分の吐いた言葉にさえ
傷、ついているもの・・・。
さと君は、
私が少し憂鬱そうにしていると、
自分の言葉のせいにして・・・
くよくよしている。
さと君はいつも、思いやりが空回り
している、のね。
さと君はさと君がひとを愛するように
自分を愛さなくっちゃ、いけないわ。
さと君に話すことは
もう、私にはありません。
さよなら、心の弱いひと。・・・・」
「さよ・・・・なら・・・。」
僕は彼女を追いかける
こともなかった。
僕は、景子さんが
僕よりずっと大人になってしまったな、
とつくづく思った。
彼女の去ったテーブルの上には
彼女の飲み残した
ティカップがあった。
淡いピンクの口紅が付いていた。
僕はじっと
ティカップの口紅を見詰めていた。
哀しい別れだとは
思いたくなかった。
ティカップを
両手で包んでみると
彼女の掌と同じ位の暖かさが
僕の心の底まで
伝わってきた。
〔十九歳〕

|
|
トップ |

